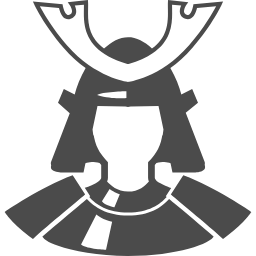偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け
 運営者
運営者
考察
まさにその『兵法』を用いた三国志の『赤壁の戦い(レッドクリフ)』では、天才軍師、諸葛亮孔明の『草船借箭の計(そうせんしゃくせんのけい)』、あるいは周瑜の『水面下の主導権』の概念が物を言った。彼らは『風林火山』の『孫子の兵法』を巧みにコントロールし、天の利を活かし、地の利を生かし、人間を過信せず、その枠の外にある力を利用した。
また、中国の名軍師、李牧は、
と言って、実に『数年』という時間を『山』に徹して勝機を待った。軍勢、情勢、外聞、体裁、天気、自然、空間、時間、決してこれらの『外部のペース』に巻き込まれない。それが、兵法を見極めた人間の立居振舞である。

例えばここで言う『自分が歌を唱う声に和唱して進む』ということを想像してみる。すると、そこに出来るのは大きなエネルギーのうねりだ。皆で大声で元気よく歌えば、前に踏み出す一歩一歩も軽快になり、行進する者の心が躍動してくる。例えば、山道を歩くと歌を歌いたくなる。今の時代を生きる日本人で言えば、宮崎駿の不朽の名作『となりのトトロ』の主題歌である『さんぽ』などがその定番である。
『歩こう♪歩こう♪わたしは、元気ー♪』
これは私も自然と歌うし、ある時テレビで軽い登山をしていた、10歳ほど年下の20代の女性タレントも、同じ歌を歌っていた。なぜかは知らないが、その淡々と続く山道を前向きに楽しく歩こうと思ったら、自然とその歌を口ずさんでしまうのだ。これは間違いなく、ここで出ているテーマと同じ的を射る現象である。
よく、戦国時代のテレビや映画や漫画には、大将がいて、その他に数百、数千人の部下たちがいて、戦争をしているシーンが出て来ることがある。戦況は必ずしも自分たちの思い通りにはいかない。時には相手のペースに押し負け、多くの仲間が戦に倒れることがある。だがそんな時、戦の中心にその部隊の大将が現われ、大声をあげてその部隊を鼓舞することがある。すると、その大将のカリスマ性があればあるほど、不利な状況で気持ちが折れかけていたはずの部隊の士気が復活し、勢いを取り戻して形勢を逆転することがある。

形勢が悪く、人数でも負けていて、いつまで続くかわからない修羅の道を歩かなければならないとき、人の気持ちはその環境に押し負けるものである。だがそんなときは思い出したいのだ。自分の内に、甚大なエネルギー源があるといことを。
※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。
こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。
🧭『38の黄金律』へ
※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。
🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る
※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。