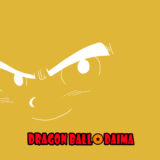第29の黄金律
『耐え忍ぶことができる人間でなければ、大局を見極めることは出来ない。』
孫子の兵法、『風林火山』の極意を見極めよ。
同じ的を射た偉人(24人)
| 革命家 | 1 |
| 政治家・リーダー | 5 |
| 発明家・ビジネスパーソン | 6 |
| 哲学者・思想家 | 1 |
| 作家・小説家・詩人 | 4 |
| クリエーター・アーティスト | 1 |
| 支配者・将軍・軍師・棋士 | 3 |
| アスリート・剣豪 | 2 |
| 科学者・学者 | 1 |
| 登山家・冒険家 | |
| 身元不明 | |
| 四聖 |
同じ的を射た書物
| 7冊 |
- 『孫子の兵法』
- 『バフェットの教訓』
- 『ユダヤ人大富豪の教え』
- 『中国古典の知恵に学ぶ 菜根譚』
- 『聖書88の言葉』
- 『言志四録』
- 『巨富を築く13の条件』
小さく負けて、大きく勝つ。そうすると、結局トータルで、自分の勝ちとなるわけだ。だが、『俺は負けない』と言って、小さな負けさえも認めることが出来ず、勝ちに執着して盲目になっている人間は、その『トータルの勝ち』を掴むことが出来ず、結果的に『トータルの負け』になってしまうことになる。
私は20代の頃、ゲームだがトランプのダブルアップの経験で、非常に重要な人生のポイントを押さえた感覚を得た。ダブルアップというのはなんてことはない。出された一枚のカードが、例えば『8』と出た時、次に来るカードがそれよりも上か、下か、を賭けるゲームである。そして、見事にそれが当たれば、持っているメダルの数が倍になる、という、倍々ゲームをひたすら続けられるというものだ。
私は以前、このゲームであまり勝ったことが無かった。なぜなら、毎回の勝負で勝とうとしていたからだ。しかし当然、毎回のようにコンピューターである相手が負けることはない。必ずどこかのタイミングで、自分の当てた賭けが外れてしまうことになる。つまり、本当は勝った経験もあるはずなのに、『トータルで負け』ていたから、『あまり勝ったことが無い』という印象が焼き付いているのだ。

それから数年後、私はゲームセンターで、『暇つぶし』でまたそのダブルアップをやることになった。この『暇つぶし』というのが、極めて重要なカギを握っていたのだ。つまり私は別に、以前のようにそのゲームで『勝とう』とは思っていなかった。映画の上映までの時間が潰れればいいと思っていた。だから、私の心は極めて冷静だった。
私は冷静に、それまでの数年間で何となく身につけていた知識、『小さく負けて、大きく勝つ(損小利大)』というギャンブルの極意を淡々と遂行しようと考えた。賭けるメダルは常に1、2枚。勝ったメダルの枚数が少ないときは、
どうせ最初から2枚しか出てこなかったわけだし、これはこのまま捨てる気持ちで、ダブルアップを強気でいこう
と考え、勝ったメダルの枚数が多かったときは、
30枚か。これは2枚の時で考えると、2⇒4⇒8⇒16⇒32で、およそ4回連続でダブルアップが成功しなければ稼げない額だから、ダブルアップしないか、やっても一度だけにしよう
と考え、勝っても負けても一切の感情を入れずに、賭けメダルの枚数を一切変えずに、淡々と手を動かし続け、機械的にメダルを増やしていくことに徹した。すると、気が付いたら手持ちのメダルはカップ一杯になっていたのである。
偶然かと思ってまた別の日に同じようなやり方でやってみると、また同じように、最初の両替金の1,000円で、同じ結果になった。隣の台の人を見ても特に順調という様子はない。明らかに自分の台だけが、自分の意志の力で順調になっているのだ。そしてその二回とも同じように、映画の上映に間に合わなくなったので無理矢理雑に使って消費させたのだった。
その後私は、FXや株式投資の勉強をする機会があった。すると私がたどり着いたこの考え方は、それら投資の世界で『最も重要』とされている損切りの考え方と同じだったことが発覚した。私はこの時、『風林火山』の極意を見たのだ。
ちなみにこれから更に数年後、この黄金律を試して部下を連れてもう一度違うゲームセンターで同じことをやった。すると、最初に両替した1,000円で見事にメダルは増えた。そしてそのメダルで違うゲーム機で更にメダルを増やした。
わかりやすいイメージ・ヒント
『アリとキリギリス』は『基礎・土台の黄金律』の件でも考えられるが、今回の黄金律でも考えられる。つまり、キリギリスは待つことが出来ず、刹那的に生きて後悔する結末を辿り、アリは耐え忍び長く生きることが出来た。
『金の卵を産むガチョウ』。この黄金律を自分のものにしたければ、この話を完全に理解するまでそこから目を逸らさないことだ。
李牧(りぼく)の戦略
現在、漫画『キングダム』の名は多くに知られるものとなった。その漫画を読んだことがある人間なら、この話の登場人物に心当たりがあるはずである。『孫子の兵法』にはこうある。
中国の戦国時代末期、趙(ちょう)の国に李牧(りぼく)という名将がいた。当時、中国の北方に匈奴(きょうど)という異民族が勢力を張り、しきりに北辺を荒らしまわっていたが、趙の国王は、なんとか匈奴の侵攻を押さえようと、李牧を討伐軍の司令官に任命した。ところが李牧は守りを固めるだけで、いっこうに討って出ない。毎日、騎射の訓練に励む一方、烽火(のろし)を整備し、間諜を放って匈奴の動きを伺いながら、部下には、
『匈奴が攻めてきても、けっして戦ってはならぬ。すぐ城内に逃げ込むがよい。』
と指示した。この結果、たびたび匈奴の侵攻を許しはしたものの、趙側の損害はめっきり少なくなった。
こうして数年経った。相手が逃げてばかりいるので、趙軍おそるるに足らずと判断した匈奴は十万余騎の大軍をもって襲い掛かってきた。間諜の知らせを受けた李牧は、さっそく奇陣を設けて迎撃し、さんざんに打ち破った。以後、李牧が健在のあいだは、さすがの匈奴もあえて趙の辺域には近づこうとしなかったという。
実に『数年』という時間を『山』に徹して勝機を待った。そして敵が油断した一瞬の隙を狙って返り討ちにし、勝利を得たのである。
風林火山
俗に言う『風林火山』とは、語呂がいいから短縮された言葉だ。本来の語源は、『風林火陰山雷』。
『 風 』
其の疾きこと風の如く。(無駄を切り詰めて風のように速く)
『 林 』
其の徐(しず)かなること林の如く。(見極めた引き際は林のように静かに)
『 火 』
侵し掠めること火の如く。(攻めると決めたら火のように燃え尽きるまで)
『 陰 』
知りがたきこと陰の如く。(陰のように気配を消して情報を得るべし)
『 山 』
動かざること山の如く。(山のように動かない時を見極めよ)
『 雷 』
動くこと雷霆(らいてい)の如し。(動くと決めたら雷のように疾く)
『風林火山(『風林火陰山雷』)』の極意を見極める人間だけが、成し得られるものがある。

草船借箭の計
例えば、映画『レッドクリフ』で有名『赤壁の戦い』で、天才軍師、諸葛亮孔明が見せた『草船借箭の計(そうせんしゃくせんのけい)』はこの風林火山の極意をマスターしていなければ出来ないものだった。
曹操が率いる『魏(ぎ)』に対抗するために劉備の『蜀(しょく)』、孫権の『呉(ご)』にてそれぞれ軍師を務める、『呉』の周瑜、『蜀』の諸葛亮孔明の二人の天才策士のやり取りの中で、『呉』と『蜀』、二国が合わさっても到底敵わない人数を誇る『魏』に対抗するために、前線で文字通り身体を張って戦いに身を投じる武将たちとは違った形で、誰にも知られずに、密かに命を懸けるやりとりがあった。周瑜は、孔明に、
『3日以内に矢を5万本用意できなければ、軍法により斬首刑に処す。』
と告げたのだ。(周瑜も、同じく別の約束をし、それができなければ同じ処罰を食らうとした。)圧倒的な数を誇る『魏』の国に、『蜀』の矢を、4万本盗まれたからである。ただでさえ不利な状況にあったのに、この責任をどう取るのか。二人が負った責任を果たすのは、容易ではない。二人が凡人なら、場は殺伐としただろう。だが、お互いは、『責任転嫁』というなすり合いをするというよりは、むしろ相手の力量を測りながら『楽しむ』、余裕さえあった。
(噂に聞く天才軍師の腕は、いかなるものか?)
この後の二人の取った行動が、叡智に溢れているのだ。周瑜の智慧については、以前書いたメタの世界にその内容を詰めたが、今回取り上げるのは、孔明の智慧である。約束から丸1日、何もしない孔明を見て、お供が焦り、言う。
『孔明さん、大丈夫なんですか!?もう後2日しかないですよ!?』
だが孔明は、『風林火山』の兵法を心得ていた。2日目、空が『濃霧』に包まれたのを見た時、『天の利』が満を持したと見極めた孔明は、たった20隻の船に”藁”を敷き詰め、『魏』の待機する船の群れに突っ込んだ。 20隻の船から太鼓で音を立てながら、見通しの悪い濃霧の中、孔明は『魏』の船に向かって、数百発の威嚇射撃をした。すると、『魏』の船は、孔明が率いる船の数を読み違え、過大評価した。その何百倍もの矢をこちらに打ちこみ、想定した数100隻の船を沈めようとしたからだ。
だが、実際は20隻。孔明は、敷き詰めた藁に相手の矢が刺さるように方向を変え、見事、矢を5万本手に入れたのだ。
退き際を見極める
世界で最も成功した投資家、ウォーレン・バフェットの著書、『バフェットの教訓』にはこうある。
穴にはまっていると気づいたとき、いちばん大切なのは、掘るのをやめることだ
(省略)1980年代初頭、ウォーレンはアルミ産業に多額の投資を行った。これは判断ミスであったが、彼はあやまちに気づくと、それ以上掘るのをやめて穴から脱出した。人は自分の間違いを認める勇気を持つ必要がある。あなたは破産したのよと、運命の女神からささやかれる前に。
間違った『支点』に、いくら『入力』しても、好ましい『出力』は出ない。
運や人生の周期を見極める
複数の会社を経営する『お金の専門家』、本田健の著書、『ユダヤ人大富豪の教え』にはこうある。
運や人生の周期を見極める
『流れと同時に大切なのは、サイクルだよ。人生には上り調子と、下り調子がある。それは、会社でも、国でも、文化でもそうだ。上り調子のときは、何をやってもうまくいく。逆に、下り調子のときには、何をやってもはずしてしまうものだ。この人生の周期を読み違えるから、良い調子で成功しかけた連中が途中で脱落してしまう。
自分の人生がどちらに向かっているか、考えなさい。いまは、ブレーキを踏むときか、それとも、アクセルを踏むときなのか、それを見極めるのだ。人生にはツキの流れがある。自分のツキがどんな状態化をハッキリ知ることが成功には欠かせない。自分のツキがないと感じるときには、思い切って何もせず、のんびり人生を楽しむことだ。
そして、運気が上昇してきて、追い風になったら、帆を大きく広げ、勝負に出るのだ。自分の運の状態を肌で感じることが出来れば、とんでもない大きな失敗をせずにすむ。とんでもない失敗というのは、運気の落ちているときに、失敗を挽回しようとして、勝負に出てしまう時に起きるものだ。そんなときは、嵐が去るまで家でじっとしておくことだね。』
この世で大富豪になった人間の意見を、真正面から受け入れよ。
うまくいかないときは力を蓄える
儒教、仏教、道教を深く学び、足りない部分を補って創り上げた、洪自誠(こうじせい)の著書であり、川上哲治、田中角栄、五島慶太、吉川栄治ら昭和の巨人たちの座右の書である、『中国古典の知恵に学ぶ 菜根譚』にはこうある。
うまくいかないときは力を蓄える
長い間羽を休め、力を蓄えていた鳥は、いったん大空に飛び出せば、必ず他の鳥よりも高く舞い上がる。また、他の花よりも早く開いたものは、散るのもまた早い。人間も同様である。なかなか仕事が成功しない、昇進しないと言って嘆くことはない。そのときに、しっかりと力を蓄えておけば、やがてうまくいく。この道理がわかっていれば、人生の途中で投げやりになることもなければ、焦って成功を求めることもない。
大富豪だろうが、そうじゃなかろうが、見る目が肥える者の意見は一致する。
待っていなさい。必ず実現するから
早稲田大学商学部を卒業後、様々な経歴を経て、クリスチャン女性の国際的なグループ『Aglow International(アグロー・インターナショナル)』に所属する中村芳子の著書、『聖書88の言葉』にはこうある。
待っていなさい。必ず実現するから
ピアニストのフジ子・ヘミングは6歳からピアノを始め、10代で才能を開花させた。27歳でヨーロッパに渡るが、貧乏なせいもあってなかなかデビューできない。35歳の時、世界的指揮者レナード・バーンスタインの援助でソロ・リサイタルを開催できる運びとなるが直前に耳が聞こえなくなり、リサイタルは失敗。その後も不遇の時がつづく。有名になるチャンスはもう来ないかもしれない。失意の中にある時に、教会でこの言葉のカードを貰う。
『遅くなっても待っておれ、それは必ず来る』
その翌99年、NHKのドキュメント番組『フジ子~あるピアニストの軌跡~』が放映され大反響に。発売したCDが爆発的に売れ、瞬く間に世界的なピアニストとなった。
夢が大きいほど、めざす山が高いほど、そこにいたる道は長くけわしい。もう無理だ、進めない、とあきらめたくなる時が一度かならずある。その時、希望を捨てずに待つ。答えが来るのが遅すぎて、あなたはしびれを切らし、待ち切れず、あきらめかけている。でも、ぎりぎりの、ぎりぎりのところで、それは遅れることなく必ずやってくる。
『聖書』
たとえ、遅くなっても、待っておれ。それは必ず来る。遅れることはない。(ハバクク書2:3)
まだだ。まだ、生きている。決してあきらめるな。
小さな利益にとらわれると、大きな利益を失う
早稲田大学を経て、情報会社・出版社の役員を歴任した岬龍一郎の著書、『言志四録』にはこうある。
役職や給料を辞退することは。たやすいことだ。だが、目先の小さな利益に動かされないことは難しい。
実際は、役職や給料を辞退することも難しいのだが、これらの辞退には、自分の意にそぐわないとの決心から出るものなので、その決意があればできる。だが、目先の利益というものは、『つい、魔が差して』と無分別な状態のときに引っかかるだけに始末が悪い。不祥事を起こす会社のつまづきは、『この程度なら』との小さな利益を優先させたときに起こっている。似た言葉に『小利を省みるは、即ち大利の残なり』(韓非子)というのがある。小さな利益にとらわれると、大きな利益を失うとの意味だ。
よい機会がくるのを待って、対応すべき
また本にはこうもある。
処理の難しいことに出会ったら、みだりに行動しては行けない。よい機会がくるのを待って、対応すべきである。私の好きな戯れ歌に、『風車 風が吹くまで 昼寝かな』(広田広毅)というのがある。
時間に焦ってはならない。その気持ちをじっとこらえ、抑え、支配するのだ。
成功の裏に秘められた想像以上の忍耐力
60年間に全世界で累計3000万部の記録的ロングセラー、ナポレオン・ヒルの著書、『巨富を築く13の条件』にはこうある。
成功の裏に秘められた想像以上の忍耐力
私は、このブロードウェイで成功した人物を何人か知っているが、その成功の秘密は、忍耐という言葉と切り離すことができない。ファニー・ハーストもその一人である。ハーストは作家として身を立てるため、1915年にニューヨークにやってきた。彼女は昼間は働き、夜は希望に燃えて著作に取り組んでいた。彼女は四年間もニューヨークの裏街道を歩き続け、そこで経験したことを題材にして、作品を書いた。彼女の希望の灯は何度となく消えかかったが、彼女はそのつど『わかったわ、ブロードウェイ、あなたの勝ちよ!』とは認めなかった。その代りこう言い続けたのである。
『ブロードウェイ、あなたがいままでに何人の人を追いだしてきたかは知らないけれど、私を追い出すことはできないわよ!諦めるのはあなたのほうだわ!』
ある出版社は、彼女に断りの手紙を36通も書いたそうである。彼女はそれでもあきらめなかった。普通の作家なら、一~二通の断り状だけで諦めてしまうものだが、蚊の条は、四年間もの間、せっせと出版社へ作品を送り続けたのである。彼女は最後に勝利を収めるのは自分だと心に決めていた。
そして、とうとうその日がやってきた。目に見えない何かの力が彼女をテストしていたのだろう。彼女はそれにみごとパスしたのである。そうなると彼女がいままで通いなれた裏道を、今度は逆に、出版社の社員が原稿を依頼するために、彼女の家に通わなければならなくなった。

待つのだ。『山』だ。虎視眈々と耐え忍び、来たる大局に備えよ。
1.日本の革命家、坂本龍馬
2.日本の指導者、勝海舟
3.日本の教育者、福沢諭吉
4.日本の海軍大将、山本五十六
5.フランスの皇帝、ナポレオン
6.イギリスの政治家、チャーチル
7.日本の経営者、松下幸之助
8.日本の実業家、古川為三郎
9.アメリカの発明家、エジソン
10.アメリカの投資家、ジョージ・ソロス
11.アメリカの経営者、スティーブ・ジョブズ
12.アメリカの経営者、ジャック・ウェルチ
13.日本の思想家、安岡正篤
14.フランスの詩人、ラ・フォンテーヌ
15.ドイツの作家、シラー
16.フランスの詩人、アンリ・ド・レニエ
17.フランスの人文主義者、フランソワ・ラブレー
18.イギリスの評論家、ジョン・ラスキン
19.アメリカの女優、ルース・ゴードン
20.日本の将軍、徳川家康
21.中国の軍師、李牧
22.日本の武将、島津義弘
23.日本のプロ野球選手、王貞治
24.日本のプロ野球選手、長嶋茂雄