仏教の開祖 釈迦(画像)
Contents|目次
内省
拠り所を探しているからこそ、拠り所が崩れたときに、自分の体調を崩すのだ。そのことについて考えたことがあるだろうか。私の母親はクリスチャンで、かつて私にこう言ったことがある。
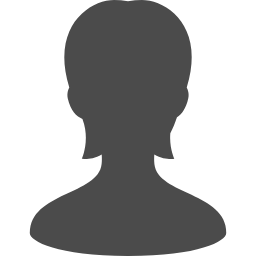 母親
母親
なるほど。宗教に心を寄せる人間の、それが本心、本音なのである。それ以上でも以下でもない。それがすべてだ。それは一言『弱さ』から来ている。全てを見てきて、死ぬほど葛藤してきた私が出している答えだ。間違いない。その『弱さ』故に、宗教に心を寄せる。ある親族には、
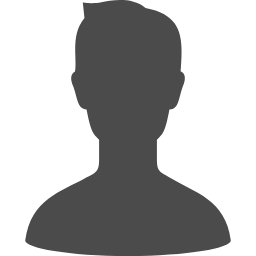 ある親族
ある親族
などと軽薄な発言を私にする人間がいたが、彼は未だにそのことについて私に謝罪することが出来ていない、臆病者である。彼は私よりもうんと年上の為、私には強く彼を批判する権利がある。彼は最初私に怯えて、敬語を使っていた。私の実の父親と同じくらいの年なのに、私が荒れた少年時代を送ったこともあり、怖かったのだ。だから、私は気を遣い、率先して話しかけてあげて、危害を加えないことをメタで(暗に)伝えた。しかし、それが彼の勘違いを助長させてしまった。
全く人というのは、怯えるか思い上がるか、落ち込むか浮つくかで、地に足がつくことのない、未熟な生き物である。宗教に対して死ぬほど悩まされ、これらのテーマについて熟考した私が『弱いから母親は宗教をやっているんだ』と言うと、『弱いからだけじゃねえだろ』と私に反論した。ちょっと前までは怯えて敬語を使っていた人間がだ。私が、『無知で、何も知らない、宗教者を馬鹿にして見下した言い方をした愚か者』の様に見えたのだろう。だが、それこそが彼が『無知』である証拠である。
私は宗教についてさんざん考え抜いてきたのだ。彼の様に、蚊帳の外でのほほんと傍観していた人間には、『到底立つことのできない境地に居る』(自分で書くことはあまりにも無様だが)と思う選択肢もあったはずだが、それを取らなかった。
自分がかつて敬語を使って怯えたことの採算を合わせようとしたこともあるだろう。 どちらにせよそんな彼に、物事を見極める見識などない。思えば彼は、幼少の頃から子供だった私に、暴言を吐くような人間だった。そういうことが積もり積もったのだろう。極めて近い親族なのに、名前すら知らないという距離感が、それを物語っている。とにかくここからわかるのはこういうことだ。
『蔓延しているからといって、その常識が正しいということにはならない』
つまりここでいうなら、『宗教をよりどころにしている人間は、大勢いる。大勢いるが、だからといってそれが正しい在り方だとは限らない。』ということなのである。
実際にブッダは、
と言って、崇拝の的となることを拒否していていた。今ある仏像の在り方も、全てブッダの教えとはかけ離れている。にもかかわらず、人は仏像に手を合わせ、何かを祈り、願い事をする。
また、ブッダはこうも言う。
つまり、そもそも冒頭で母親が言った、
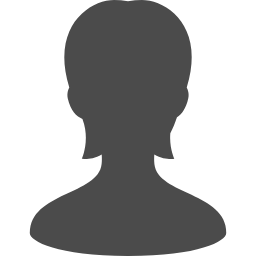 母親
母親
というセリフは、的を突いているようで、外しているのだ。そして、その的を外した常識が、さも『それっぽい』から、蔓延しているのである。
更に一歩踏み込んで考えるのだ。自分が崩れたくないという理由で、特定の神に身を委ねることは、自分本位ではないのか。その思想は、自分で選んでいるからして自分の意志。それを揶揄されたり攻撃されることは耐え難く、時には攻撃し返すこともある。それが不和であり、確執であり、戦争である。だとしたらその委ねた宗教は、人間の在り方として間違っている。そもそもが、自分が助かりたいという私利の気持ちから、発展しているのだ。
『諸行無常』とは、この世の現実存在はすべて、すがたも本質も常に流動変化するものであり、一瞬といえども存在は同一性を保持することができないことをいう。世界は、諸行無常なのだ。最初から、そうなっているのだ。だとしたら、『自分が崩れない為に何かに身を委ねる』という発想は、そもそも間違っているのだ。自分は、いずれ崩れるのだ。それが、宿命なのだ。それを理解すればこっちのものだ。
ブッダは言う。
『私はかつて、拠り所を求め世界中を探究してみたけれども、グラグラ振動せず移ろいゆくことのない安らかなところなど、どこにも見つからなかった。』
固執、執着、依存。これがあるからこそ、人は憂い、悩み、苦しむのである。人間だけではなく、この世における生きとし生ける者全ての生命が等しく、儚く、そしてだからこそ厳かで尊いのだ。私も、母も、その親族も全て、平等の命なのである。
参照文献
経集937、法句経277。
関連する『黄金律』
 『自分の心と向き合った人間だけがたどり着ける境地がある。』
『自分の心と向き合った人間だけがたどり着ける境地がある。』
 『流動変化が避けられないことを知っているかどうかは、人間の運命を大きく変える。』
『流動変化が避けられないことを知っているかどうかは、人間の運命を大きく変える。』



