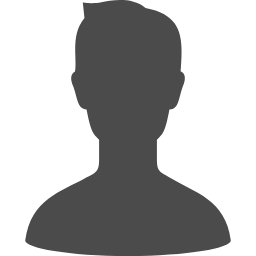名言と真剣に向き合って、偉人の知恵を自分のものにしよう!
 運営者
運営者
考察
まず単純に、薬による副作用ということもある。薬を飲んで、強制的に抑えることが、他の要素の活動も抑えることになり、それが原因で衰弱してしまう、というデメリットということもある。サプリメント依存症や、摂食障害の人間のことを考えてもそうだ。以前、摂食障害の少女が、『サプリメントで栄養は摂っているから大丈夫』と言って、一日に、たった一つのコッペパンだけ食べて過ごしていた。彼女は身体を壊してしまった。
人間というものは失ってから初めてものの大切さに気付くものだ。彼女のビタミンは、確かにサプリメントの影響もあって、足りていたが、それはあくまでも断片的な評価に過ぎず、後の要素がボロボロだったのだ。私はその一件を通して、
でも、サプリメントはやっぱり意味はあるんだ。それに依存して他の食事を極端に減らすから問題になっただけで、健康の補助として摂れば、しっかり補えるんだなあ
と思ったが、同時に、健康に関する無知の怖さを知ったものだった。
また、もう一つここに付け加えることは、『薬の災い』の、違う解釈についてだ。前述したような『薬による後遺症、副作用、デメリット』という、直接的な話ではなく、『薬を摂取する、依存することによって失うものがある』という『災い』についてだ。世界的に著名なアメリカの細胞生物学者であり、ウィスコンシン大学医学部やスタンフォード大学医学部で教鞭をとる、ブルース・リプトン博士の著書、『思考のすごい力』には、このテーマに関する重大な事実が記されている。
1952年、イギリスで、ある掛け出し医師がミスをした。そのおかげで、医師アルバート・メイソンは、短い間ながら学界でもてはやされることになる。 メイソンは15歳の少年のイボを催眠療法で治そうとした。イボの治療に催眠療法が適用されることがあり、かつ成功率も高く、メイソンもそれまで経験を積んできた。(訳註:イボはウイルスの感染によるものだが、 催眠によるイボの治療は当時広く行われており、治癒率はかなり高かったという。 だが、なぜ催眠によってイボが治癒するのかは解明されていない。)
ただし今回は厄介なケースである。肌がごわごわになっていて、人間の肌というより、まるでゾウの皮膚のようなありさま。しかも全身がその状態で、まともなのは胸だけ。ある外科医が皮膚移植で治療をしようとして断念し、メイソンに少年を任せたのだ。
最初の治療で、メイソンは片方の腕に焦点を絞ることにした。少年を催眠状態に導き、この腕はイボが治って健康なピンクの肌になる、 と暗示を与えた。一週間たって再びやってきたとき、治療を施した腕はかなり良好な状態になっていた。 メイソンは喜び、少年を外科医のところに連れていった。だがそこで、メイソンは自分が医学上のミスを犯していたのを悟った。腕が治ったのを見て、外科医はびっくり仰天した。メイソンには伝えてなかったのだが、少年の腕はイボではなく、先天性魚麟癬(ぎょりんせん)という、 命にかかわる遺伝病によるものだった。
この病気の症状を精神力『だけ』で治すことなど、とうてい不可能だと考えられていたのだが、メイソンと少年はそれをやってのけたのである。メイソンが引き続き少年に催眠療法を施すと、最初に治療した腕と同じように、 肌のほとんどは治癒して、健康的なピンク色に戻った。少年はグロテスクな肌のために、学校で情け容赦ないいじめを受けていたが、 その後は普通の生活を送れるようになった。
メイソンが魚麟癬の驚異的治療について、 1952年に『英国医学雑誌』に報告すると、大騒ぎになった。メディアが派手に書きたてたために、致命的で、かつ良療法が見つかっていない、 この奇病に悩む患者たちがメイソンのところに押しかけた。だが結局、催眠療法は万能ではなかった。メイソンは何人もの魚麟癬の患者に催眠療法を試みたが、 あの少年と同じような結果は、ついぞ得られなかった。メイソンは、治療に対する確信の無さが失敗の原因だと考えた。少年を治療したときは悪性のイボだと思い込んでいて、必ず治せると自信満々だったのだが、そのあとの患者の治療にはそういう態度で 臨む事が出来なかったという。
非常に興味深い内容である。
※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。
当サイトにある500人の偉人の8000の名言は、ぎゅっと集約して『38』にまとめられます。人間がいる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。
『38の黄金律』へ
名言一覧
Pickup名言
 名言AI
名言AI
 ヴィルヘルム・ミュラー『機会を待て。だがけっして時を待つな。』
ヴィルヘルム・ミュラー『機会を待て。だがけっして時を待つな。』  ウラジーミル・レーニン『若い青年の最も重要な課題は、学習である。』
ウラジーミル・レーニン『若い青年の最も重要な課題は、学習である。』  トーマス・フラー『妻は絶えず夫に服従することによって彼を支配する。』
トーマス・フラー『妻は絶えず夫に服従することによって彼を支配する。』