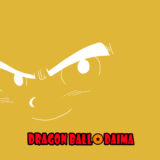第32の黄金律
『流動変化が避けられないことを知っているかどうかは、人間の運命を大きく変える。』
流動変化するこの世の真理を知り、それに最適化し続けよ。
同じ的を射た偉人(28人)
| 革命家 | |
| 政治家・リーダー | 1 |
| 発明家・ビジネスパーソン | 11 |
| 哲学者・思想家 | 5 |
| 作家・小説家・詩人 | 5 |
| クリエーター・アーティスト | 4 |
| 支配者・将軍・軍師・棋士 | |
| アスリート・剣豪 | |
| 科学者・学者 | 1 |
| 登山家・冒険家 | |
| 身元不明 | |
| 四聖 | 1 |
同じ的を射た書物
| 11冊 |
- 『バフェットの教訓』
- 『組織の盛衰』
- 『上位20%に入れる人だけが一生成功する』
- 『お金がお金を生むしくみの作り方』
- 『やわらかな生命』
- 『単純な脳、複雑な「私」』
- 『価格、品質、広告で勝負していたらお金がいくらあっても足りませんよ』
- 『奇跡の経営』
- 『人生を変える80対20の法則』
- 『ありのままに、ひたむきに』
- 『小さいことにくよくよするな!』
この世は流動変化している。
時間は流れ、宇宙はうごめき、命の火は消え、物質は分かれる。風は吹き荒れ、大地は鳴り響き、海は揺らいで、炎は燃え盛る。
それなのに、自分の命や、家族の命、自分の価値観、時代の流れ、作り上げたビジネスが、そのまま永久不変として残っていくことを願うのは、いささか、思い違いもいいところである。そんなに永久不変のものに依存したいなら、うってつけのものがある。それは、『この世は流動変化している』という事実だ。その事実なら、永久不変として、変わることはない。この世の真理である。
わかりやすいイメージ・ヒント
最初からこの世が何一つ固定されていないということがわかれば、自分の心から『消えるべき感情』が何かが分かる。
この『流動変化』が『真理(いつどんなときにも変わることのない、正しい物事の筋道。真実の道理。)』なわけだから、それに逆らった行動は全て、真理ではない(間違ったことである)。
時代遅れの原則は、もう原則でも何でもない
世界で最も成功した投資家、ウォーレン・バフェットの著書、『バフェットの教訓』にはこうある。
時代遅れの原則は、もう原則でも何でもない
ある日の朝、ウォーレンは目覚めとともにはっと気づいた。恩師グレアムから学んだ投資原則は今の時代に通用しないと。(中略)ウォーレンは従来の航路を踏み続けることをせず、船から飛び降りて新たな投資哲学を採用した。永続的な競争優位性を持つ優良ビジネスを相応の価格で買い、上げ潮の収益と時間が株価に反映されるのをじっくり待つという投資哲学だ。これは、ウォーレンを金持ちから超金持ちへと押し上げていった。
何といっても、時代は流動変化している。この決定的な事実を真正面から受けいれれば、話はもう終わりだ。
消え失せた『花形産業』
東京大学経済学部を卒業後、通産省に入り、日本万国博覧会を企画し、開催にこぎつけた立役者、堺屋太一の著書、『組織の盛衰』にはこうある。
消え失せた『花形産業』
(省略)さて、この『就職のしおり』の1950年前後の版を見ると、かなり好成績の東大生が集中している業種の一つが、石炭産業であったことがわかる。当時の石炭産業は正に『花形』、全国所得番付でも、ベストテンの半数以上を石炭業者が占めていた。
(中略)ところが、この石炭産業、わずか20年後にはほとんどの企業が斜陽化し、40年後の今(1993年)ではまともな企業は皆無といってよい。芸術の進歩や需要の変化で、消え失せた業種業態は少なくない。
(中略)どうしてそんなことになってしまったのか。その最大の理由は、『環境への過剰適応』にあったといえる。(中略)石炭労使は、この点についても理解を欠いていた。自己の政治力を過信して、政府も『石炭を潰すことはできない』『産炭地域を見捨てるはずがない』と信じ続けていた。ヒト余り、モノ不足社会に過剰適応していた石炭産業は、環境の変化を知りたくなかったのかもしれない。
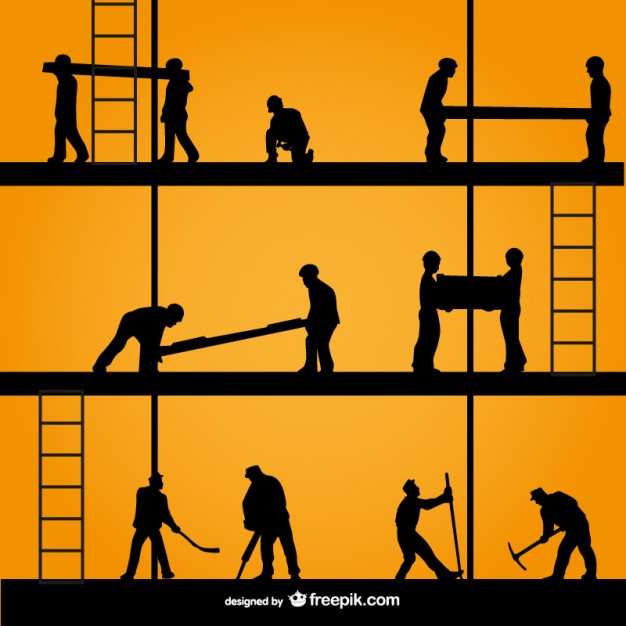
得意体質の強化に走る過剰適応性
ある環境で発展した生物は、環境変化にさらされると自らの体質的特色、いわば得意の体質を一段と強化することで危機に対処しようとする。人間の組織も同様で、環境の変化で危機的状況になると、これまでの環境で有利だった体質を一段と強めることで生き残ろうとする。特定の環境に過剰適応した組織は、その特色が顕著なだけに、それが著しい。日本の石炭産業も、その例外ではなった。
世は流動変化するのだ。それを受け入れられるか、られないかだ。
上位20%の人は、変化を愉しむ
SBIモーゲージ取締役執行役員常務、横山信治の著書、『上位20%に入れる人だけが一生成功する』にはこうある。
上位20%の人は、変化を愉しむ(その他の人は安全地帯にしがみつく)
人間は変化を恐れる生き物です。もっと上のステージに行きたいと頭で考えていても、自然と身体や脳は、今いる安全地帯に留まろうとします。それは遺伝子に組み込まれた、危険から身を護るために備わっている、安全装置のようなものだと私は認識しています。上位20%の人に共通することは、変化を恐れず常に上のステージを目指し、実際に行動しステージを上げていった人達です。人類も同じように、変化を恐れない人たちが開拓した歴史でつくられています。
『最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残ることが出来るのは、変化できる者である。』byダーウィン
流動変化するのだ。それに対応できるかどうかだ。
未来を予測する頭のいい方法
人間のお金に対する考え方のパラダイム転換を説いた、ロバート・キヨサキの著書、『お金がお金を生むしくみの作り方』にはこうある。
未来を予測する頭のいい方法
どんなものでも、いずれは『時代遅れ』と言われるようになる。ならば、過去から未来を予測し、時代を先取りしよう。
『Big tomorrow』2009年5月
(省略)産業時代の従業員は、長く勤めれば勤めるほど経験をつむことができた。情報時代は、経験の長さが『負債』になりかねない。(中略)その一方で、私は、年配の技術者を、『学び続けて成長し、未来を読み解けるようになろう』と励ますことも忘れていない。未来を見通す『ビジョン』のないリーダーシップなどありえない。未来を予測する一つの方法は、『現在』を『過去』としてとらえてみることだ。この情報時代では、自分の考え方が時代遅れになっていることに気づかない人ほど危険きわまりないものはない。
この件に関して不安になる必要はない。ただ『これらの真理』から目を逸らさず、時代のうねりの甚大な実力を理解すればいいだけだ。
常に分解されている自分の身体
京大卒の生物学者、福岡伸一の著書、『やわらかな生命』にはこうある。
シジフォスの労働
すべてのことが不透明で、不確かなこの世界にあって、次の二つのことだけはいつの世でも真実である。第一に、人の心は変わるということ。第二に、人は必ず死ぬということ。(中略)私たちはふだん自分は自分、自分のからだは自分のものと思っている。けれどほんとうは、私が私であることを担保する物質的基盤は何もない。私の身体は流れの中にある。分解と合成のさなかにあり、常に新しい原子や分子が食物として取り入れられ、その時点で私を構成している原子や分子は捨てられる。
(中略)ゆえに記憶も実は流れ流されている。全身のあらゆる部位が常につくりかえられている。一年もすれば、物質的には私は別人となっている。だから心がどこに宿っているにせよ、それは変わって当然なのだ。むしろ常に変転し続けている。
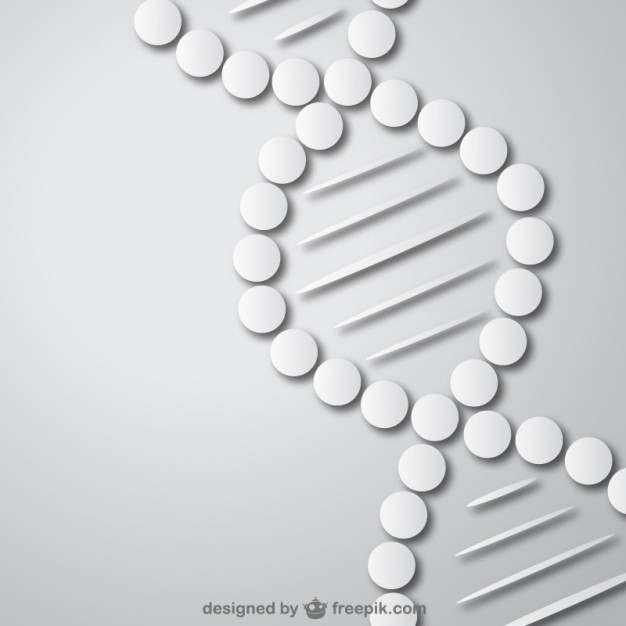
自分の身体の中でさえ、常に流動変化している。
どんな一流の人間でも脳は揺らいでいる
権威ある脳科学者、池谷裕二氏の著書『単純な脳、複雑な「私」』にはこうある。
(タイガー・ウッズやイチローといった超一流選手が、あれほどまでに努力を重ねているのに、土壇場になってプレイに乱れが出てしまうことがあるのはなぜか。)
たとえ同じ場所、同じ距離、同じクラブと、全てを同じ条件して打ったとしても、なぜかうまくいくときと、いかないときがあるんだ。それはなぜかって話。(中略)では、その握力の強弱は、何によって決まるのか、というのがこの論文。結論から言うと、それは『脳の揺らぎ』で決まる。
(中略)──ゆらぎ。そう。回路の内部には自発活動があって、回路状態がふらふらとゆらいでいる。そして『入力』刺激を受けた回路は、その瞬間の『ゆらぎ』を取り込みつつ、『出力』している。つまり、『入力+ゆらぎ=出力』という計算を行うのが脳なんだ。となると『いつ入力が来るか』が、ものすごく大切だとも言えるよね。だって、その瞬間のゆらぎによって応答が決まってしまうんだから。結局、脳の出力はタイミングの問題になってくる。
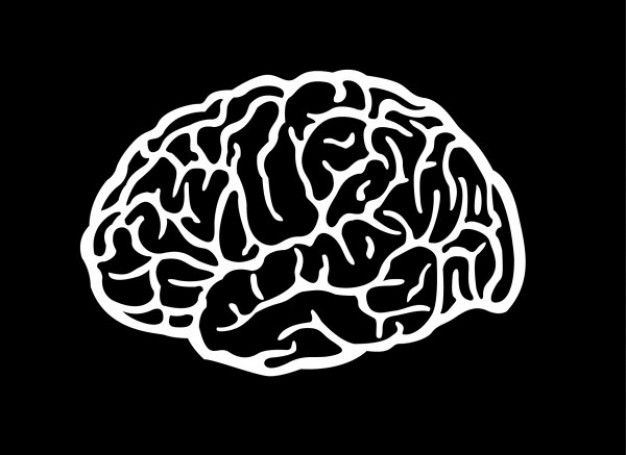
脳にも『ゆらぎ』がある。固定されていないのだ。
売れ続けるために必要な『XとYの法則』とは?
広告電通賞、ACC賞等を多く受賞するクリエイティブ・ディレクター、川上徹也の著書、『価格、品質、広告で勝負していたらお金がいくらあっても足りませんよ』にはこうある。(登場する人間の人間性うんぬんではなく、『知識』に目を向けるべきである。)
売れ続けるために必要な『XとYの法則』とは?
(省略)いわゆる一発屋と呼ばれる方々と、長期にわたって安定してテレビに出続けている人たちとの差はどこにあるのでしょう?その違いをとてもわかりやすい明快な理論で説明している人がいます。20代の頃、『紳助竜介』という漫才コンビで一世を風靡し、その後はバラエティ番組の司会などを中心としたタレントとしてテレビに出続けている島田紳助氏です。(中略)そこでは『XとYの法則』とでも名付けるべき理論が展開されています。要約すると以下の様な内容です。
成功する人間は、努力と才能の掛け合わせた値の大きい人間だ。才能についてはわからないが、努力は方法によって成功する確率は格段に上げられる。しかしそのためには、『自分の戦力、自分に何ができるか(=X)』と『時代の流れ(=Y)』を綿密に分析し準備してから戦わなければならない。そして売れるためには、XとYで交わるように仕組んでいく必要がある。しかし、たいていの人は、XもYもわかっていないまま悩んでいる。だから売れない。
でも時として売れてしまうことがある。やっていること(X)は変わっていないのに、Y(=時代の空気)は絶えず変化していくので、いきなりそれが合致してしまうことがあるからだ。そしてその方が出合い頭の事故なので、インパクトが大きい。でも、たいていの場合は、偶然の事故なので、本人も自分がなぜ売れたのかわかっていない。公式がないから、根拠がない。自分のXもYもわかっていないため、Y(=時代の空気)が移り変わると、必ず潰れてしまう。いわゆる一発屋になってしまうのだ。
現代の日本人なら『一発屋』の話はわかりやすいはずだ。我々は一体何人見ただろうか。偶然の勢いに乗り、そしてその勢いが未来永劫続くと過信してしまい、転落してしまった人間たちを。
真の変革とは?
リカルド・セムラーの著書、『奇跡の経営』にはこうある。
真の変革とは?
(省略)われわれにしてみれば、変革を恐れるよりも競争相手やテクノロジー、消費者から、三行半を下されることのほうが恐ろしい。だからこそ、ビジネスを存続する為に絶えず変革しています。古いことわざに『転がる石にはコケが生えない』があります。その別のバージョンとして、『変化する会社は、過去のしがらみを逃れる』が言えると思います。何か問題が起きたなら、今の在り方を変える。また何か問題が起きたのなら、もう一度変える。変わり続けることこそが、解決策となるのです。
均衡は幻想
リチャード・コッチの著書、『人生を変える80対20の法則』にはこうある。
均衡は幻想
永遠に続くものは何もないし、ことに均衡は儚い。永続的なものがあるとすれば、それはイノベーションだけである。イノベーションはつねに抵抗に出合い、多くの場合進行が遅れるが、死に絶えることは稀である。イノベーションに成功すれば、生産性はいまよりはるかに高まる。ある一線を越えると、イノベーションの勢いには誰も抵抗できなくなる。個人であれ、企業であれ、国家であれ、めざましいイノベーションに取り組んだからといって成功するものではない。もう誰にも押しとどめようがないところまでイノベーションを進めた場合のみ、成功するのである。生き残るためには改革が欠かせない。何がもっとも効率的かを発見し、そこに全力を集中するには、建設的な改革が欠かせない。
世界は『変わり続けて』いる。その中で、確かに自分の意志だけは断固として揺るぎないものとしてそれを貫くことも出来るかもしれないが、しかし、どんな人間であろうと絶対に体内で行われる分解と合成、脳や心の『ゆらぎ』を制止させることはできない。だとしたら、自分の意志もまた同じように、流動変化していることになる。

すべてのものごとは、一瞬もとどまることなく変化していく
浄土真宗本願寺派、第25代門主、本願寺住職、大谷光淳の著書、『ありのままに、ひたむきに』にはこうある。
仏教には『諸行無常』という言葉があります。すべてのものごとは、一瞬もとどまることなく変化していく。そして、その一瞬ごとにすべてのものごとは変化しながらかかわりあっているのです。人との関係も固定したものではなく、当然、変化し続けています。一人ひとりが輝いて、いまの自分自身と他人のいのちを互いに大切に生きていける関係こそ、人と人とが支え合いながら生きていく素晴らしい姿だと思います。
人生のすべては流転する
心理学者でストレス・コンサルタントのリチャード・カールソンの著書、『小さいことにくよくよするな!』にはこうある。
これは私が二十年前に学んだ仏教の教えだ。このおかげで、ものごとをあるがままに受け止めるという客観的な見方を身につけることができた。この教えの本質は、人生のすべては流転するというところにある。すべてに始まりがあり、終わりがある。木は種から芽を出し、やがて土に返る。すべての岩は形成されては消えていく。いまの世の中でいえば、どの車も機械も衣類も生産されて使い古されていく。すべては時間の問題だ。私たちは生まれ、やがては死ぬ。グラスはいずれ壊れる。
この教えは心の平和をもたらしてくれる。すべては壊れると思っていれば、そうなったときも驚いたり失望しないですむ。なにかが壊れてもぎょっとするかわりに、それをもっていた時間に感謝するようになる。
諸行無常
2,500年前、仏教の開祖、ブッダ(釈迦)は言った。
時間は流れ、宇宙はうごめき、命の火は消え、物質は分かれる。風は吹き荒れ、大地は鳴り響き、海は揺らいで、炎は燃え盛る。
全ては流動変化している。それが、諸行無常の言葉の意味である。2,500年も前の言葉が、未だに廃れることなくこの世の智恵としてその輝きを失うことが無い。この事実を受け入れられたなら、見えて来る道がある。
ホンマでっか!TVの特集『時代の変化』
追記:2018年5月に『ホンマでっか!TV』で特集されていた『時代の変化』についてまとめておく。
2018年5月
- リモコンの巻き戻しが消え、『早戻し』になった
- 小学校1,2年生の授業から理科と社会が消え『生活科』になった
- ササニシキが食べられなくなる
- 暴走族が消えた
- ハンコがなくなりつつある
- 街からスズメが減っている
- デパートの屋上から遊園地がなくなった
- 料理本から『4人分』の表記が消え、『2~3人分』になった(少子高齢化等の影響)
- スーパーからカリフラワーが消えつつある(ブロッコリーが人気になった)
- 英語の筆記体がなくなりつつある(喋るのが優先)
- 教科書から坂本龍馬が消える
- 駐車違反のチョークが消えた
- J-POPから『愛』が消え『好き』になりつつある
- 缶切りが使えない子供が増えた
- 鉛筆の主流が『HB』から『2B』になった
- 夫婦の間で『あなた』と呼ぶことがなくなった
- コテコテの関西弁がなくなりつつある(東京弁を使う人が増えた)
2018年10月
- 図書館の本を消毒するようになった
- お坊さんが墓参りをネットで配信するようになった
- ℓの表記が小文字から大文字になった
- 結婚式の共同作業がケーキカットから『カラードリップケーキ』になった
- 日傘男子が増えた
- 病院へ行かなくてもオンライン診療できるようになった
- 飛行機の中のドクターコールがなくなり、ボランティアの登録制になった
- 廃校が水族館になったりするよになった
- 死んだ後に見られたくないPCデータを消去できるサービスができた
- トイレの混雑に応じて男女切り替え可能になる動きが出ている
- 近隣に配慮し、盆踊りがイヤホンをつけて無音に(無音フェスも)
- 小学生から脱毛サロンに行く子供が増えた
- 遺灰を3Dフィギュアに入れる考え方が増えた
- 医者が聴診器を首から下げなくなった(ばい菌対策)
- レジや駅の券売機でお金が下せるようになる
- ヨーロッパの影響力がなくなってきた
- 『バツイチ』が『マルイチ』になりつつある
- 『貧乳』が『シンデレラバスト』になりつつある
2019年5月
- 苦い薬が無くなりつつある
- 集合写真の上の隅表示が消えつつある
- 美容室から「雑誌」が消えつつある
- トンネルの「オレンジ照明」が消えつつある
- 学校給食からパンが消えつつある
- 会社から「転勤」が消えつつある
- ハイカットの「バッシュ」が消えつつある
- 日本で「赤いてんとう虫」が消えつつある
- いちごスプーンが無くなりつつある
- ドラマの雨の中での告白が消えた
- エレベーターの天井にある「救出口」が消えつつある
- 日本から「和式トイレ」が消える
- 学校から飼育小屋が消えつつある
- 「ネイリスト」がいなくなる
- 結婚式の「ブーケトス」が消えつつある
1.アメリカの大統領、トマス・ジェファーソン
2.日本の経営者、永守重信
3.日本の経営者、鈴木敏文
4.日本の経営者、石坂泰三
5.日本の経営者、井植歳男
6.アメリカの経営者、ジェイ・エイブラハム
7.アメリカの発明家、エジソン
8.日本の経営者、生田正治
9.日本の経営者、岩崎彌太郎
10.日本の経営者、弘世現
11.日本の経営者、松下幸之助
12.アメリカの経営者、ジャック・ウェルチ
13.フランスの実業家、ココ・シャネル
14.フランスの哲学者、ヴォルテール
15.イギリスの哲学者、ラッセル
16.日本の思想家、瀬戸内寂聴
17.フランスの哲学者、モンテーニュ
18.ドイツの哲学者、ショーペン・ハウエル
19.イギリスの作家、アラン・シリトー
20.古代ギリシャの詩人、エウリピデス
21.日本の作家、山本周五郎
22.ドイツの作家、ゲーテ
23.アイルランドの作家、スウィフト
24.日本の漫画家、やなせたかし
25.日本の映画監督、小津安二郎
26.日本の芸術家、岡本太郎
27.アメリカのジャズトランペット奏者、マイルス・デイビス
28.仏教の開祖、ブッダ(釈迦)